ハイブリッドカー ( Hybrid Car ) とは、作動原理が異なる二つ以上の動力源をもち、状況に応じて単独、あるいは複数と、動力源を変えて走行する自動車のこと。自動車のエネルギー効率は、"Well to Wheel" (油井から車輪)までの総合効率で考える必要があるが、ハイブリッドカーは総合効率が電気自動車や燃料電池自動車と同程度であり、環境負荷の低い実用車として注目されている。
広義のハイブリッドカーには、エンジンの排気エネルギーをターボチャージャーの排気タービンを介してその回転力を回収し、クランク軸(出力軸)に戻す「ターボコンパウンドエンジン」までもが含まれる、他に、CNG自動車・水素自動車の一部も燃料にCNG・水素とガソリンの両方を持ち切り替え可能であるため、一般には「バイ・ヒューエル」と呼ばれるが、海外ではハイブリッドと呼ばれる場合や、例えばミニバンとオフローダーの中間的車種が新たに出た場合にもハイブリッド車種と呼ばれる場合がある。
以下では1997年に発売されたトヨタ自動車のプリウスが契機となって一般への普及が始まっている、内燃機関と電動機を組み合わせた、「化石燃料 + 電気式のハイブリッド車」 ( Petroleum Electric Hybrid Vehicle ( PEHV ) )を中心に記述する。
内燃機関(以下エンジン)に蓄電池(以下バッテリー)と電動機(以下モーター)を組み合わせたハイブリッドカーの普及にはガソリン自動車黎明期の20世紀初頭と21世紀初頭の2度のピークがある。
ただし、その目的は「調速の容易さ」と「低燃費」とで異なる。ガソリンエンジン自動車が普及を始めた20世紀初頭においては、その性能において 蒸気自動車や電気自動車に劣っていた。特に、蒸気貯めに圧力を蓄えたり鉛蓄電池に電気を蓄えたりするため始動トルクが大きく、ニードル弁や抵抗器操作で無段階変速が可能な2者に比べ、ノッキングなど低速性能が悪くアクセル・クラッチ・減速ギヤないしプーリー切替の同時操作を強いられるガソリン車の操作性は劣悪であり、複雑な精密機械であるトランスミッションの故障も多かったため敬遠された。
そのような中、ガソリンエンジン車の唯一の利点である(軽量高カロリーのガソリン燃料に依る)航続距離の長さを生かす道が、内燃機関→発電器→整流器→蓄電池→電動機のシリアルハイブリッドだった。しかし第1次世界大戦を経て機械工作の精度が向上し、「軽量高信頼性のトランスミッション」や「油式トルクコンバーターによるノンクラッチ車」が登場するに及んで「複数の動力を制御する複雑さ」「内燃車と電気車のシステムを合わせた重量の問題」や、その結果によるコスト増が明らかになりハイブリッドカーは廃れていった。
しかし、1997年にトヨタ・プリウスが市販されて以来、多くのハイブリッドカーが公道を走るようになった。エネルギー源に化石燃料を用いる場合、従来のガソリンスタンドでの給油のみで、距離の制限なしに走行が続けられるため、新たなインフラ整備を行う必要がない点も普及の後押しとなった。さらに、夜間電力などの利用で、さらなる有害物質やCO2の排出と、運行コストの低減が期待できる、家庭用電源による充電機能を追加したプラグインハイブリッドカーの開発も複数の自動車メーカーから発表されている。
走行時の環境負荷の低い自動車としては、電気自動車、水素自動車、燃料電池車の排気がクリーンでエネルギー効率が良い。しかし、製造コストが高い、充電時間が長い、常温で気体である水素の充填量が増やせない(燃料タンク容積に対し取り出せるエネルギーが少ない、つまり充填1回当たりの走行距離が少ない)、水素充填のためのインフラ整備が財政負担となるなど、多くの問題があり、いまだ開発途上にある。
また、ハイブリッド車の補助動力の蓄積には、二次電池以外にキャパシタや圧縮空気、フライホイールなども試行されているが、エネルギー蓄積量やコストの面から、現在のところは乗用車用としては二次電池を用いるのが一般的である。ただ、二次電池は充電/放電のエネルギー損失が大きく反応が遅いため、ハイブリッド建設機械やハイブリッドトラックの一部には高性能キャパシタが使われている。
なお、ハイブリッドカーは電池とモータを積んでいるという特徴を生かして、最近ではさらに電気自動車寄りに進化させた発展型のハイブリッドカーが開発されている。例えば、電池式電気自動車とハイブリッドカーの利点を合わせた「プラグインハイブリッドカー」や架線式電気自動車(トロリーバス)とハイブリッドバスの利点を合わせた架線式ハイブリッドトロリーバスなどがそれである。(詳細:電気自動車参照)
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン以外を発電用動力とする研究としては、プジョー、ルノー、ボルボの各社がガスタービンエンジンを使用する研究を進めているが、実用化には至っていない。これらは小型ガスタービンを発電専用としたシリーズ方式である。また、プジョーではこれとは別に、ヨーロッパで人気のあるディーゼルエンジンとの組み合わせで、ハイブリッドカーの市販化を目指している。
| ハイブリッドカーの種類。(ハイブリッドシステム) | |
| 「パラレル方式」 主役がエンジンで、モーターがサポート役の エンジンによる走行が主体。発進時に最大の力が出るモーターの特性を活かし、エンジンが燃料を多く消費する発進・加速時に、モーターでサポートする方式。従来のクルマにモーターとバッテリーなどを追加するだけのシンプルな機構。 |
|
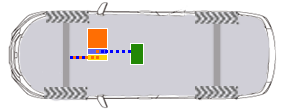 |
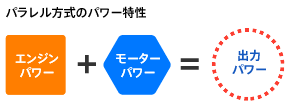 |
| 「シリーズ・パラレル方式」 低速はモーターだけで走り、速度が上がるとエンジンとモーターが助け合う発進・低速時はモーターだけで走行し、速度が上がるとエンジンとモーターが効率よくパワーを分担。動力分割機構や発電機などがあり構成は複雑。エンジンは発電機も回す。 |
|
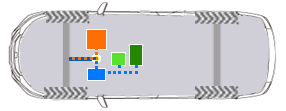 |
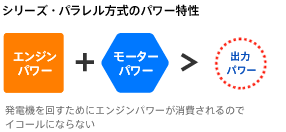 |
| 「シリーズ方式」 モーターだけで走る電気自動車、エンジンを発電機の動力としてのみ使用し、モーターだけで走る方式。動力機構そのものは電気自動車ですが、エンジンを搭載しているためハイブリッドカーの一種に含まれる。 |
|
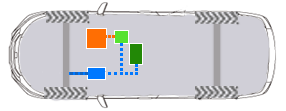 |
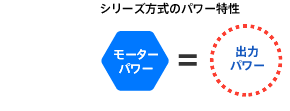 |
