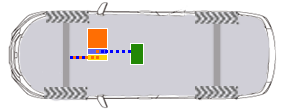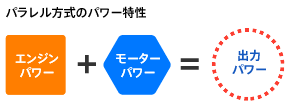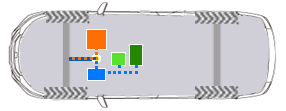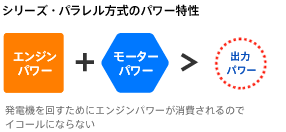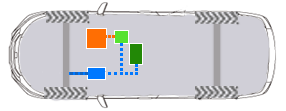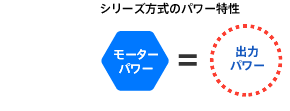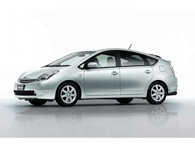- 長さ3.40m以下
- 幅1.48m以下
- 高さ2.00m以下
- 排気量660cc未満
となっている。
ナンバープレートの色は、自家用は『黄色地に黒文字』、事業用は『黒地に黄色文字』である。
②軽自動車の特徴は
- 車両本体価格のほか、税金・保険料などの維持費も安い
- 車体が小さく取り回しが容易
- 下取り価格が比較的高い(例外あり)
などである。
マイカーの利便性が高い(道路が発達して渋滞が少ない、ロードサイド店舗が発達している、公共交通機関の便が悪い)地方では、個人の通勤・買物等での移動手段という文字通り「足」として、一世帯で複数台の自動車を所有することが一般的である。その際コストを抑えるため、セカンドカー(一世帯で保有する二台目以降の車)に軽自動車を購入する例が多い。セカンドカーの使用者は、女性或いは運転免許を取得して間もない若年者などであり、軽自動車の中心的購買層である。
③現在の軽自動車は、バブル期のビート、カプチーノ、AZ-1等の趣味性の高い車を除き、総じてハッチバック型の2ボックスか、またはミニバンの軽自動車版と言った1ボックスがほとんどであるが、これは実用性を重視したためである。 軽自動車のサイズが限られているため、4人乗りでセダンのような独立したノッチバック形状のトランクルームを設けようとした場合、現在の日本人の体型では後部座席が窮屈になったり、仮にトランクを作っても大きさの制限があるために、ごく小さいものしか作れない。 実際にフルモデルチェンジ後のオプティは4人乗りでありながられっきとした独立したノッチバック形状のトランクを持っていたが、1990年代末期から現在の基準としては比較的狭いものであった。
 |
 |
 |
 |
 |
 |